|
|
|
●釜屋解体
H16年2月20日過ぎから数日間、コンクリートの解体をしました。ハンマーなどで少しずつ解体していくと、更に下から別の時期にはったと思われるコンクリートが・・・。現在は上の部分だけを解体しています。
また、年代によって柱や床板などの表面の加工の仕方が異なっていることがわかりました。加工道具の違いのようです。
(H16.2.24記) |
 |
 |
 |
| コンクリート解体 |
下に覗くのが以前のコンクリート |
少しずつ丁寧に |
 |
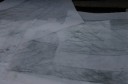 |
 |
削り方の比較をするために
トレースします |
数種類のトレース |
壁土が止まりやすくする為に
加工をしています。
網目は珍しい。 |
 |
 |
|
| 天井の梁の部分 |
天井を覆う竹 |
|
|
|
|
|
|
●釜屋解体と中蔵片付け
釜屋の解体も土壁を取り除く工程に入りました。写真のように場所別に保存をして、復元の際の資料にするようです。
釜屋内部はそのほとんどに足場が組まれ、全体を見渡すことは出来ません。
最近、「結構静かだなぁ・・・」と感じ、見学に行くと、ハケで丁寧に掃除をしていました。時折、エアーコンプレッサーの「プシュッ!」という音が響きます。
2月17日、善導寺職員総出で中蔵の片付けをしました。(蔵と言っても現在は改装して小部屋などに変っていますが・・・)
現在の状態を撮影する為に、荷物の移動をしたり、処分したりして空の状態にしました。
全てが生活空間のため、引っ越ししたい荷物を何処に置くか悩みどころです。事務を止める訳にはいきませんので、事務用品などは近場に置いておきたいが、すぐに解体に入るので置けません。新たに倉庫を作るにしても、全てが工事区域で簡単には作れません。
こんな状況の為、廊下に出しっぱなしの箇所もあります。参拝の方々には大変ご迷惑をお掛けしております。ご理解の程お願い申し上げます。
(H16.2.21記) |
 |
 |
 |
| ハケで丁寧に掃除 |
壁土を標本化 |
エアーを吹き付けて
埃を飛ばす |
 |
 |
 |
| 天井裏(土埃) |
土壁が解かれ、
竹の骨組が残る |
壁土も保存 |
 |
 |
 |
|
中蔵
(現:旧福岡教務所) |
中蔵
(現:旧応接室) |
 |
 |
 |
| 応接室看板 |
撮影状況 |
旧福岡教務所 |
|
|
|
|
|
●釜屋解体・・・日に日にその姿が変わっていきます。
図面を書き、寸法を測り、撮影をして、番付を書き、解体して、掃除をして、撮影をして、資料として残す。
図面などを見せてもらうと、床板1枚1枚細かく書かれています。また、上からは見えなかった床下の柱などまで書かれています。数年前、実際に床下にもぐって調査したようです。
解体した物1つ1つをしっかり撮影して倉庫に格納するそうです。後程、撮影の状況を報告しようと思いますが、シャッターを何分も開けて隅々までピントが合うようにして撮っています。振動や光の影響を受けないように、夜中に作業をしています。此の時期は非常に寒いのです。もちろんストーブなどは持ち込めません・・・。
そして、このように膨大な資料を残すことも、文化財修築に与えられた使命だそうです。
単に、古くなったから、修理するだけじゃないんですね・・・。
(H16.2.8記) |
 |
 |
 |
工事前の釜屋に入っていた
物(日用品)を収納する倉庫を
作ってくれています。 |
床板がはずれました。
明治時代あたりの修復状況の
ようです。 |
解体した床板を釘の穴や
細かい溝をブラシで丁寧に
掃除をしています。 |
 |
 |
 |
解体した物には1枚ごとに
「番付」(その板がどこに使用されて
いたものか)を記入していきます。 |
ズラリと並ぶ番付。
目にしただけで、大変根気の
いる作業とわかります。 |
|
 |
|
|
工事とは別に、古文書などの
資料調査もすすむ |
|
|