|
|
|
●本堂内部の壁・倉庫内での調査
毎日春らしく暖かい日が続き、外に出るだけで汗が出てくるようになりました。
本堂では内部の壁を剥がし、補強し、塗り始めています。
内部といえどもやはり痛みも残っていて、今にも落ちそうなグラグラな壁などもありました。
大規模な塗り替えは計画していないので、部分修理を丁寧に作業しています。
また、倉庫内を覗いてみると、解体を完了した大庫裏の部材が所狭しと並んでいました。
それを1つ1つ丁寧に記録をとり調査をしているのが、文建協の技術者の方々。柱にある釘の痕跡や汚れ、日焼けの跡などから、「当時はここに○○があったみたいですねぇ」などの想像が広がる。「な〜るほど!」と思うことばかり。「すごいっ!」の一言に尽きます。 |
 |
 |
 |
| 本堂内部、裏堂の壁を剥がす |
様々な技術で補強し
部分補修をする |
 |
 |
 |
|
本堂西側「火燈窓」の補修 |
 |
 |
 |
| 倉庫内 大庫裏の部材 |
竹串を刺しているのは、釘穴の向きを調べているようです。
この場合はナナメに打ち込まれているので、斜めに傾いた
庇(ひさし)のようなものが取り付けられていたのではない
かと判断できるそうです。このように、細かな釘の穴も見落
とさず調査し、図面におこして当時の姿を甦らせるという作
業をしてくれています。 |
|
|
|
|
|
●本堂内部の修理始まる
3月27日〜29日の開山忌も無事成満し、いよいよ平成17年度が始まりました。
大庫裏の解体も完了したので、現在は本堂の修理を行っております。3月末まで縁板と東面、西面、北面の建具や壁を補修しました。今回から南面の建具と壁、そして内部の壁の補修にとりかかっています。
まず、内部の畳をとり、そこに足場をかけていきます。内部がかなり狭くなりました。
3月20日の大地震、そして4月20日の大余震。その後も何度か大きな余震がおきています。「もぅ、そっとしておいてっ」という感じです・・・。
(H17.5.7記) |
 |
 |
 |
正面の大きな桟唐戸
(さんからど)の取り外し |
正面に足場 |
内部足場が設置される
所の畳をあげる |
 |
 |
 |
|
水引も取り外し |
いよいよ足場が |
 |
 |
 |
| まず東面から |
庫裏から本堂に入ると
こうなっています |
5月6日 本堂にて安全祈願式 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● 全文連 文化財保護研修会
その名のとおり全国の文化財の所有者で構成されている「社団法人 全国 国宝 重要文化財 所有者連盟(全文連)」の研修会が善導寺で開催された。
4月28日、午後1時半、北は宮城、南は鹿児島まで全国から文化財の所有者や関係者の方々約90名が善導寺に集まった。
研修はまず、文化庁文化財部参事官(建造物担当)参事官付文化財調査官の上野勝久氏より「建造物保存の課題と意識改革について」と題し講演をいただいた。
次に、現在、善導寺保存修理の設計監理に携わっている【財】文化財建造物保存技術協会九州支部 善導寺設計監理事務所長の東坂和弘氏より「善導寺大庫裏他六棟の保存修理について」と題し、善導寺が文化財として認められたいきさつや、現在の修理の状況、更には文化財や建造物からうける心のゆとりなどの精神的な面のお話もして頂いた。
その後、2班に別れ善導寺の修理状況を見学し、解散となった。
国宝や重要文化財はやはり寺院や神社が多い。しかし、同じ寺院でも宗派などの違いにより交流は少ない。浄土宗としては知らない人はいないほどの「大本山善導寺」だが、参加者からは「九州にこういうお寺があるとは知らなかった」「近くに住んでいるのに今日初めて来ました」などの声が多くあった。
文化財を所有しているという誇りや素晴らしさ、しかし守っていく大変さや苦労などをおしゃべりしながら、有意義な研修会ができ、善導寺も「平成24年の完成までしっかり行動していかなければ!そして自分達の力だけで保存できるように勉強せねば!」と改めて思った。
(H17.4.29記) |
 |
 |
 |
| 大楠会館2階で研修 |
文化庁 上村調査官の講演 |
 |
 |
 |
| 文建協 東坂所長の講演 |
約90名の参加者 |
解体完了した大庫裏の見学 |
 |
 |
|
| 修理中の本堂の見学 |
解体を控えている書院の見学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
● 本堂内部に足場
平成17年4月より文化財保存修理の為、本堂内陣の壁の補修にとりかかりました。
法要はできるように計画しておりますが、随分狭くなり、参詣の皆様には何かとご不自由をおかけ致しております。
各種団体様で本堂をご利用予定の方は、お問い合わせ頂くか、一度下見にいらして下さるようにお願い申し上げます。
平成17年7月末頃までこの状態が続く予定です。
尚、その後も今回の地震で被害を受けた壁などの補修の為に、別のところに足場がかかる予定です。本堂の完成は平成18年3月頃の予定です。
(H17.4.22記) |
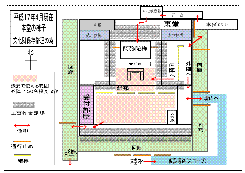
クリックで拡大 |
|
|
|
|
|
|