|
|
●大庫裏 瓦葺き
10月に入り、大庫裏をはじめ第2期工事、専称寺の作業もどんどん進み大きく変わってきました。
まずは大庫裏の瓦葺き。 奈良の職人さんが毎日作業しています。 全て手作りで約2万枚ともいわれる平瓦を綺麗に葺いていきます。 そして丸瓦。 屋根の形、見た目を左右するだけに数ミリの狂いも許されない作業。 さらに、1枚割れても雨漏りしないように3枚重ねに葺いています。 普通の屋根よりも数倍の手間がかかっています。
現在は、棟を残した状態で一旦おやすみ。 準備が整ったら取付します。
(H18.10.23記)
|
 |
 |
| いよいよ平瓦が葺かれます |
きれいにまっすぐ |
 |
 |
| 2万枚並べます |
3枚重ねになっています |
 |
 |
| 左2枚は古い瓦、右2枚は新しい瓦 |
最高の職人さんが葺いてくれています |
 |
 |
| 端の瓦も特殊なものを作って3枚重ねに |
隅の瓦を据えるのは難しい |
 |
 |
| 見てて安心する 建物らしい見事な曲線 |
ほぼ完成 あとは手直し |
 |
 |
| 棟の部分は後日の作業 |
大庫裏の軒丸瓦(巴瓦) 〔綺麗に撮れたました…〕 |

これは本堂の鬼瓦です 〔綺麗に撮れたました…〕 |
|
|
|
●大庫裏 壁工事 (小舞かき・荒壁塗り)
屋根工事と並行して壁工事にもとりかかりました。
竹を丁寧に並べ、縄で編んでいく。 内側から荒壁土を塗る。 塗り圧を考えながら均一に塗る。 裏なでをした後、返し塗りをする。
この後にも中塗り、仕上げなどの工程が続く。 左官の仕事は、壁ができあがってはじめて「商品」となる。 そしてそれまでの工程の技術はそこには見えない。 今のうちにこの技術の素晴らしさを報告しておきます!
(H18.10.23記)
|
|
 |
 |
| 竹小舞と荒壁塗りの下準備 |
荒壁塗り |
 |
 |
| 裏に”にゅっ”と出てくる |
この後、返し塗りに入る |
 |
 |
| 大庫裏 内部 |
乾燥状態も良好 |
 |
| 暗くなるまで作業が続く |
|
|
|
●大庫裏 素屋根解体
2年前、平成16年8月に建て始めた大庫裏の素屋根が、そろそろその役目を終わろうとしています。
大庫裏屋根の瓦葺きの完了に伴い、素屋根の屋根部分を解体しています。 今回の工事始まって以来最大の65トンのクレーン車が力を発揮。 2台のクレーン車で巧みに運びながらスムーズに解体していきます。
側面の部分は壁塗りや仮通路のために、もうしばらく残します。
|
 |
 |
| 2年以上工事を守った大庫裏の素屋根 |
屋根のトタンが外される |
 |
 |
| クレーン車2台で裏の駐車場にパーツを運び解体する |
 |
 |
| 鳶さん達 怖くないのでしょうか? |
小さなパーツが数百個組み合わされ、このようなトラスになり、これが数十本組み合わされて屋根を構成していました。 |
|
|
|
|
●第2期工事 仮設通路の設置
工事はすでに第2期工事の準備に入っています。 2期工事は、書院や広間、役寮の解体をします。 善導寺の中心にある建物が全て工事区域となります。 つまり、残っている建物は、西に本堂、三祖堂、東に大楠会館、北に新庫裏だけということになります。 現在、工事区域となる書院等を取り囲むように、仮設通路が設置されています。
(H18.10.23記)
|
 |
 |
| 大楠会館より本堂へつながる通路 |
本堂側からみたところ |
 |
 |
| 新庫裏から本堂裏堂へ続く通路 |
平成24年頃までの5年間使うので、
基礎をコンクリートで固めました |
|
|
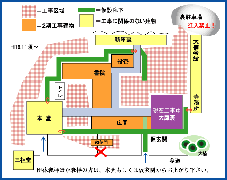
仮設通路などはこうなります(クリック) |
|
|
|
●北野町 専称寺 解体進む
明治5年に善導寺より移築された建物が、2Km離れた北野町専称寺に現存していることが分かり、調査と協議の結果、善導寺に再移築することが決まった。
本年8月には解体工事に着手。 現在は小屋組みの解体が全て完了し、礎石だけとなった。
専称寺では、土地の調査が入ったあとはすぐに新築の庫裏を建設します。 また、善導寺に運び込まれた当初の部材は、倉庫で調査や繕いが行なわれ、平成22年頃復原される予定。
(H18.10.23記)
|
 |
 |
| 庫裏解体中の専称寺 全景 |
クレーンを使って小屋組みを解体 |
 |
 |
| 思った以上に当初材があるようです |
礎石だけになりました |

礎石の調査 |