● 釜屋 発掘開始
● 書院 解体
大庫裏が完成し、次にとりかかったのは大庫裏北側に位置する 「釜屋」 部分の発掘作業。 この釜屋は、平成16年1月からの修築工事の一番最初に解体した建物。 同5月の発掘では地下から巨大なカマド跡を発見した。 その他の建物の工事の為に、一旦丁寧に埋め戻されたが、今回再発掘が行なわれ、3年ぶりにカマドが姿を現した。 このカマドは釜屋の建物と共に復原する予定。
広間、書院、役寮・対面所の部分も天井などの解体が行なわれており、現在の状態を、こと細かく記録・調査されている。
また大庫裏も、南側の安全通路が解体され、立派な姿を見れるようになった。 今後は周辺の塀や縁などの組立てにとりかかる。
(H19.4.21記)
|
 |
 |
| 釜屋部分の発掘作業始まる |
3年前の発掘後、土嚢を詰めて丁寧に
埋め戻された部分を取り除いていく |
 |
 |
| 3年ぶりに顔を見せたカマド跡 |
どう復原されていくのでしょうか? |
 |
 |
書院解体現場
ほとんどの壁が取り外されました |
天井の図面・・・傷みの状態などを
細かく調査し書き込んでいます |
 |
 |
大庫裏南側の安全通路解体
2年9ヶ月間お世話になりました |
通路が外され南側からの
眺めが良くなりました |
 |
 |
| 以前の大庫裏 (平成12年頃) |
現在の大庫裏 |
| 復原、保存修理というものはこういうことなのかと実感! |
|
|
|
|
● うきは市「平川家住宅」視察
● 大庫裏 完成!
大庫裏の完成直前に福岡県うきは市浮羽町にある 「重要文化財 平川家住宅」に出かけた。 ここは現在修理中の建物で「くど作り」のかやぶき屋根。ここには「竹天井」があり、善導寺の大庫裏の一部に同じ竹天井があることから、設計管理者、職人さんと一緒に視察した。
善導寺最大の行事、開山忌大法要(3月27日〜29日)の直前に大庫裏が完成しました。(隣の建物等の兼ね合いで一部未完のところもあります)。 見事に250年前の状態に復原された大庫裏を見渡しながら、「当時の人々は何を思ったのだろう」と考えてみたりしました。 ただ、現代人の私どもは、柱や作りに時代の重みを感じることはできますが、今からこの空間を一体どう使ったらいいのかイメージが沸きません。 これからの課題です。
(H19.4.2記)
|
|
 |
 |
| 平川家住宅 |
平川家 内部 |
 |
 |
| 平川家 竹天井 |
平川家 釜 |
 |
 |
| 善導寺 大庫裏 南側 |
内部 建具の取り付け |
 |
 |
| 竹天井の取り付け |
職人みんなで一気に仕上げました |
 |
 |
| できました! (南西の部屋) |
現代人のために踏み段を作ってくれました |
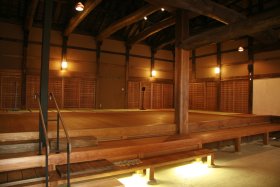 |
 |
| いい雰囲気です (南東側より撮影) |
畳も入りました (北西側より撮影) |
|
|
|
●大庫裏 完成間近! 広間・書院 解体
暖冬と呼ばれていますが、3月に入ると肌寒い日が続いています。 しかし、筑後川沿いは満開の菜の花、本堂前の桜も開花しました。
保存修理工事は、3月末の大庫裏完成に向けて急ピッチで作業が進められています。 床面、上がり段、建具、や畳、電気や防災設備の作業もしています。 3月27日から3日間の善導寺最大の行事、「開山忌大法要」には内部を通行できるようになります。
(H19.3.17記)
|
|
 |
 |
| 大庫裏・・・足場がとれ、外観が現れました |
玄関の鬼瓦と妻飾り |
 |
 |
大楠会館への渡り廊下ができたので、
今回復原された大庫裏の玄関が隠れました |
大庫裏南面の妻飾りの部分に
墨を差しています |
 |
 |
見事に復原された大庫裏南面の懸魚(げぎょ)
かなり巨大です |
六葉の部分
これから古色仕上げされます |
 |
 |
| 大庫裏内部 床を張っています |
床を止めるのに使う和釘 |
 |
 |
電気系統、防災設備のパネル
(過去に戻った建物に最新の設備が…。
不思議な空間です…) |
北面の足場も取れました
壁の色がナナメに変わっている茶色の部分は
今後「釜屋」が取り付く場所です |
 |
 |
広間・小書院の天井
解体調査も本格的に |
内仏の装飾は「剥落(はくらく)止め」を
施してから解体します |
|