|
●釜屋の屋根工事始まるほか
夏休みも終わり9月に入りました。 朝晩は涼しい日もあり過ごし易くなりましたが、日中はまだまだ残暑が厳しく、体力を奪われます。
「釜屋」の組立ては屋根面の竹野地・杉皮葺きが終わり、いよいよ瓦が葺かれはじめました。 また、屋根の下では「カマド」の復原が着々と行なわれています。
「広間・書院・役寮」などの一体は、ただひたすらに解体・調査が行なわれています。 時々取材に行くと、廊下の屋根が無くなっていたり、床が取り外されていたり、ゆっくり丁寧に調査が進んでいます。
(H19.9.8記)
|
|
|
 |
 |
| 大庫裏の北側に釜屋 |
釜屋組立て中(北側) |
 |
 |
| 竹野地だけでは強度が足りないことから、竹の間にステンレス製のパイプを通すことになった |
 |
 |
| パイプに竹と同じ色を塗っています |
竹野地ができました |
 |
 |
綺麗に編みこんでいます
写真中央付近にパイプがあります |
色の濃いところは、以前の竹を再利用した部分です
(全体の5分の1程度再利用) |
 |
 |
| 次に杉皮を葺いていきます |
下地が竹で、途中ステンレスのパイプもあるので大変です
|
|
|
|
 |
 |
| こちらにはカマドの復原を待つ「石」たちがいます |
カマドの復原が始まりました |
 |
|
見事に元通りに組み上がっていきます
|
|
|
|
|
 |
 |
| 本堂西の空地で、釜屋の壁土を作っています。 左官さんとその弟子が足で土を混ぜています! |
|
|
 |
 |
| 大庫裏北側の庇(ひさし)部分の組立て |
釜屋との兼ね合いもあり、釜屋と同時に作っています |
 |
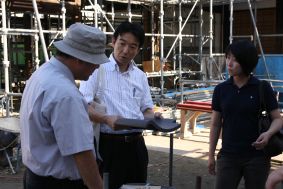 |
| ここも竹野地 |
奈良から瓦も到着しました |
 |
■今回も奈良県の橋本瓦葺工業さんが来てくれています。 特殊な桟瓦(さんがわら)なので、思い通りに葺くのが難しいようです。 |
| いよいよ瓦の葺き始め。 |
|
|
|
|
 |
 |
小書院(来迎殿)部分です
少し解体しては調査・調査…その繰り返しです |
広間部分は床が解体されました |
 |
 |
| 小書院東側の廊下…→ |
…も、解体 |
|
|
|
 |
 |
| 以前、一般のトラックがぶつかって破損した、大門の軒先を修理してくれました |
|
|
 |
 |
| 三祖堂の天井裏へ調査に入りました |
三祖堂天井裏
中央の人影は調査員です(亡霊ではありません) |
 |
■安産祈願所として有名な「三祖堂」は、文化財にこそ指定はされていませんが、随分古い建物で、屋根瓦のズレ、ひどい雨漏り等、老朽化が進んでおります。 堂内に安置の「善導大師」「当寺開山
聖光上人」のご尊像は国の文化財でもあり、安産祈願等で毎日参拝者の絶えないお堂でもありますから、今回の第二次平成大修築で修理の計画をたてております。 先日から、その痛み具合を調査していただいております。 本堂と比べると小さなお堂ですが、一般寺院の本堂くらいの規模がありますので、大変な工事になりそうです。 |
はい、身軽な大工さんです
取材班は入口から覗いただけです。怖いので… |
|
|
|
|
 |
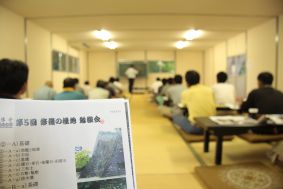 |
毎月行なわれている「修復の極地 勉強会」は今回で5回目。(8月31日)
今回は礎石や石垣などの「石」についての勉強会でした。 |
|
|
|