|
|
●基礎工事 と 勅使門屋根工事 ほか
広間ではいよいよ組立て。 礎石の設置が始まりました。
書院・役寮は1月末に発掘調査が終わり、基礎コンクリート打設。
勅使門(表玄関門)では、屋根の銅瓦葺きの作業が行われています。
(H21.2.22記)
|
|
|
 |
 |
| 広間では礎石の設置、土台の設置がおこなわれています |
 |
 |
| ここも大庫裏や釜屋と同じように「ひかりつけ」で土台を置いていきます。 職人さんたちも慣れてきたようです。 |
防災訓練
消防署の方に指導をしていただきました。 |
|
|
|
|
|
 |
 |
| 書院も発掘が終わり基礎の下地を作り始めました |
捨てコンの上に鉄筋を組みました |
 |
 |
| 全ての建物を一体化する為、30台を越すミキサー車が来て、基礎コンクリートを打設。 |
|
|
|
 |
 |
勅使門の屋根 丸瓦の部分が木材でできあがりました。
平瓦の部分に砂漆喰を塗って乾燥 |
 |
 |
作業倉庫内では、銅瓦葺きの職人さんが、銅の部分のパーツを準備しています。
「銅板葺き」ではなく、この「銅瓦葺き」は、手間のかかる高級な仕上げの為、九州ではなかなかお目にかかることができなく、また、こういった作業も現場でやることが少ないようで、今回、たいへん貴重な資料を残すことができました。 |
 |
 |
| たくさんのパーツに分かれています。 |
大きさの見本として置いてみました |
 |
 |
| 先ほどのパーツをカシメていきます。 雨が漏らないように水の流れを考慮して組み上げていきます。 |
 |
 |
一方、大工さんは鬼瓦にあたる部分の下地を作りました。
これに銅板が巻かれることを考慮して、形作っていきます。
このままでも充分立派なものですが…。 |
 |
 |
出来上がった鬼瓦の下地に銅板を打ち造型していきます。
厚いところ、薄いところを作りながら、平らな銅板に起伏をつけていきます。 |
 |
 |
| 何度も打ち、何度も整形して完成していきます |
棟の部分にも銅板が巻かれました |
|
|
|
|
|
 |
 |
| ここは水琴窟の周辺。 現状保存を指導されていて、甕などを掘り出して調査することができませんので、水琴窟の設置年代がハッキリしていません。 発掘作業の時に周りの土から年代を割り出そうと調査中。 はたして、正確な結果は出たのでしょうか…? |
|
|
|
 |
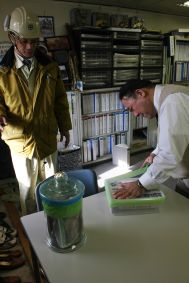 |
こちらは、書院の基礎コンクリート中に納める、地鎮の為の「鎮め物」を集めました。
お経本などの他に、写真やDVD、(DVDプレーヤーも…)現代の資料となるものを詰め込みました。 ほとんどタイムカプセル状態ですが、はたして何年後に開封されるのやら・・・。 200年後でしょうか? 500年後でしょうか? 気の遠くなるようなお話ですが、250年前の江戸時代の人だって、250年後に平成という時代が来て、その建物が残っていて、未来の人々がこんな大規模な工事をするなんて思ってもみなかったことでしょう。 必ず100年後、200年後は来るのです。 その時代の人々が、平成の時代を邂逅してくれたら嬉しいです。 (そんな話をみんなでしながら、埋めました。) 善導寺の物だけではなく、日本のいろいろな資料や現代の日常の生活や想いなども手紙にして入れています。 役に立つかなぁ…。 (その前に、形として残っているかなぁ…?) |
 |
 |
| はい、埋めました。 この上に、基礎コンクリートが打設されます。 目印でも無い限り、私たちでもわからなくなります。 さて、未来の人々は気付いてくれるでしょうか? |
|
|
|
|
|
 |

19年秋の大公開より
大鋸挽きの実演
迫力のあるページになりました! |
善導寺の文化財工事が始まって5年が過ぎたので、「5年アルバム」と題し、写真集を作ってみました。 内容はページ数の制約もあり、公開事業や関係者のイベントが中心です。 (あくまで個人的なものですので、もちろん個人出費の非売品。) 今後、広報係として、内容の濃い、文字や数字がいっぱいの資料だけでなく、こういった写真集などをパラパラとめくり、文化財工事のことを楽しみながら理解してもらえる作品を、きちんと作れたらいいなぁと思っています。 このホームページの修築コーナーも、そうであったらいいなと思います…。
|
|
|
|
|
●年明け 発掘調査 と 勅使門の組立て
明けましておめでとうございます。
お正月も過ぎ、1月5日から作業が開始されました。 まずは今年一年の工事の無事を願い、工事関係者一同で「安全祈願式」を行いました。
「広間」では基礎のコンクリートがはられ、礎石が据えられようとしています。 「書院・役寮」は、発掘で出土した甕棺などが取り出され、埋め戻しが始まっています。 現在、役寮の南部分の発掘が行われており、1月末に発掘終了の予定です。
一方、「勅使門(表玄関門)」では屋根部分が綺麗にできてきています。 仕上がりは「銅瓦葺き」になるようです。
(H21.1.23記)
|
 |
| 工事関係者全員で新年の安全祈願をしました |
 |
 |
| 書院は基礎工事に着手 |
役寮南側の発掘調査
左側の広間部分には礎石が並び始めました |
|
|
|
|
|
 |
 |
| 勅使門の屋根工事 |
野地板 |
 |
 |
| 丁寧に作られています |
1つ1つが綺麗です |
 |
 |
| 立体的で綺麗なカーブを描いています |
蓑甲という部分・とてもカッコイイです |
 |
 |
| 野地を作ります・土居葺き |
竹釘 |

|
←屋根屋さんの道具。
●作業
1・口の中に竹釘を数十本、パクッ!とほうり込みます。
(※良い子はマネをしないように)
2・口をモグモグさせると、竹釘が頭の部分を前にして、口から出てきます。
3・道具の真ん中の膨らんだ部分を利用して、釘をサクッと板に挿します。
4・道具の先の方でトントントントンと打ち込む。
この工程がわずか数秒。 ものすごいスピードで何枚もの板が固定されていきます。
職人の業を見せてもらいました。 |
 |
|
 |
とても綺麗に仕上がってます。 まだまだ工程は続きますが、
最終的に、銅瓦葺きの仕上げになるようです。
あまりお目にかかれない仕上げなので、出来上がりが楽しみです。 |
|