|
|
●「広間」 いよいよ完成間近!
7月上旬、ほんのひとときの梅雨の合間の晴天からまた一変、ゲリラ豪雨や大雨が続き、三祖堂内の大雨(?雨漏り)や善導寺境内がプール状態になった時もありました。 幸い大きな被害はなく、ひと安心しました。
この様なお天気状況でしたので、書院・役寮などの「茅葺工事」は一向に進みませんでした。 しかし、7月中旬以降は、夏日(すでに猛暑)となり、作業再開。 もともと工事の進捗が早かったので、残すは棟の部分だけとなり、予定通り7月中には完成できそうです。
一方、7月末までに完成する「広間」は、「表玄関」上部の彫刻に極彩色が塗られ、また龍などの彫刻も、業者の作業所で着々と仕上がっているようです。 広間内部の壁は、当初(江戸中期)と同じ赤い土壁になりました。 広間の大半は将来、寺務所となりますので、実用性を考えて畳ではなくオフィスフロアが敷かれました。 この部分は、8月後半からの三祖堂修理に伴い、仮の安産祈願所として数年間使われる予定です。 また、渡り廊下などに塗る、「漆喰壁」の土を作る行程も見学させていただきました。 初めて見る光景で、想像つかなかった作業に驚きました。
今年の夏も暑くなりそうです。 熱中症などにならないように気をつけながら、作業をしていただきたいと思います。
(H22.7.21記)
|
|
 |
| 「茅葺」 隙間を埋めるために短い茅を差し込んでいく |
 |
 |
| 棟の部分の工程に入った |
完成まであと少し |
 |
 |
| 広間表玄関上部の彩色 「下塗り」 |
極彩色に仕上がっていきます |
 |
 |
| 完成しました |
華やかな色です この周りに龍などの彫刻が飾られます |
 |
 |
| 広間内部の赤壁の土 |
赤い壁が塗られています |
 |
 |
| 広間内部 オフィスフロアが敷かれました |
本堂の東下屋の屋根補修も |
 |
| 漆喰壁を作ります |
 |
 |
| 海草を煮ます。 数時間で固形物が無くなるので、それを濾(こ)します。 |
 |
 |
| 麻の繊維を入れます |
混ぜます |
 |
 |
| 石灰を振るいにかけながら入れます |
混ぜます |
 |
 |
| 白い壁土が出来ました! |
一方、左官小屋前では、寝かした壁土を少しずつ軟らかくしながら、現場へ運んでいました。 |
|
|
|
|
|
●タマ監督、出世!?
現場に住み着いたネコの「玉監督」ですが、『現場をウロウロ、本当の現場監督のような行動がおもしろい!』ということで、地元の読売新聞の方が取材に来られ、7月10日に「読売新聞・ちくごかわらばん」という折込新聞1面に紹介されました。 また、翌週には「西日本新聞・九州版」にも掲載され、広く知られるようになりました。 記事を読んだ方々から、「明るく、ほのぼのした優しいニュースで癒されました。 玉監督に会いたいです。」と数件の感想が寄せられました。 人にも優しい文化財の建築をしています。 動物にも優しくありたいものです。
「善導寺に頼もしい助っ人が登場! 足しげく現場を見回って愛嬌を振りまき、熟練の職人達の心を一つにまとめる雄の子猫、人呼んで玉監督。 「タマホーム」と命名された寒さをしのぐ為の宿舎を建ててもらい、最近はテニスボールを半分にした建設用ヘルメットも作ってもらった。安全は何より大事。 雨の日はタマホーム、暑い日は日陰でこっそり昼寝。 ネズミやヘビを見かけると夢中で追い回し、行方知らずにもなる気ままな仕事ぶりだが、全国各地から来ている棟梁や職人らの心は、ガッチリとらえている! 緊張感あふれる現場で、みんなを癒し、元気付けてくれる玉監督はかけがえのない存在。 おかげでチームワークは抜群です。」 (読売新聞掲載原稿抜粋、一部編集)
素晴しい文章を書いていただいた記者の方に感謝します。
|
 |
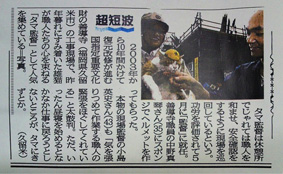 |
| 読売新聞・筑後かわらばん 7月10日 |
西日本新聞 7月17日朝刊 |
 |
 |
ヘルメットがお気に入り
(普段はかぶってません…) |
取材の時間は眠そうでした… |
 |
 |
| 西日本新聞の取材の様子。 取材中にもかかわらず、本当の現場監督さんの足を枕に、とうとう眠り始めた玉監督……。 |
|
|
|
|
●広間内部工事 ・ 表玄関(勅使玄関) 漆塗り
梅雨に入り、雨が降ったり止んだり、蒸し暑い季節になり、職人さんたちにとって大変な季節になりました。
7月末の完成を目指して、広間では内部工事が着々と進んでおります。 天井や床が張られ、壁工事や表玄関の漆塗りが行われています。
表玄関の両側の壁は、解体調査でわずかながら「朱漆」の塗られた痕跡が見つかりました。 京都からいらした漆職人さんが、6月中旬の一週間かけて、綺麗に仕上げていかれました。
(H22.6.24記)
|
|
|
 |
 |
| 広間の天井が張られた |
広間の壁工事も進む |
 |
| 本堂への渡り廊下も最終工程へ |
 |
 |
表玄関
漆にほこりの付着を防ぐために、シート内での作業 |
まずは「柿渋」を塗り重ねること3回。
1度塗ると、そのあと「磨き」という作業が入るので、
工程としては6行程となる |
 |
 |
いよいよ「朱漆」を塗る
これも3回重ね塗り |
これが朱漆 (しゅ・うるし) |
 |
 |
| ムラ無く綺麗に塗り上げる |
1ヶ月くらいすると本来の色に落ち着くようです |
|
7月に入ると、玄関の彩色や彫刻にとりかかります
|
|
●文化財保存修理工事 一般公開 『茅葺大公開』 6月19日(土)
平成15年に工事が始まって以来、今回で9回目となる一般公開は、書院などの茅葺屋根工事を中心に、表玄関の漆塗りや彩色の紹介、広間の壁塗りの実演などの見学ができ、久留米市内外より約270名の見学者が来場しました。
茅葺は、今年4月より書院、役寮および対面所などが葺かれており、公開用のために作られた専用スロープより屋根まで上がり、間近に見ることができ、また屋根面を整える作業を実際に体験することもできました。
茅は、熊本県阿蘇市から仕入れ、重さ約30トン、12000束に及びます。 それを下地の竹組みから約60センチの厚さで敷き詰め、突き板などで型を整えます。完成すると屋根面積は620平方メートルと広大で、文化財の中では九州最大となります。
見学者からは、「昔は良く見た光景だが、最近は見なくなった。 とてもなつかしい。 茅の匂いが心地いいですね」、「この厚さで雨をしのぐんですね。 通気性もよさそうで、夏は涼しいのでしょうね」 と、今は失われつつある技術に感動していました。
一般公開も終わり、安全面の都合でもう間近で茅葺を見ることはできませんが、足場が取れれば迫力のある屋根がお目見えします。 書院や役寮の茅葺は7月末に完了の予定。 広間は同じく7月末に復原完成し、実際に使用できるようになります。
(H22.6.24記)
|
|
|
|
|
 |
 |
| 広間内で壁や漆の説明 |
京都の漆職人さんも丁寧に説明してくれました |
 |
 |
大カマドではお湯を沸かし、恒例のお茶接待。
釜屋だけ、とても熱かった……(汗)
スタッフのみなさんお疲れ様でした |
平成18年11月の書院解体から、発掘、組立て、上棟式、
そして現在の茅葺までの工事記録映像の上映 |
 |
 |
| 書院、対面所の茅葺屋根の見学 |
みんなヘルメットをかぶり、見学スロープから屋根面へ |
 |
 |
| 間近で茅に触れることができるのは今回の公開だけ |
茅葺職人さんからの説明 |
 |
 |
善導寺の茅葺面は 寄棟(西側)、切妻(南側)、入母屋(北側)など様々な屋根の形の屋根があり、
非常に珍しく、高さも違う屋根が見事につながっています。
様々な茅葺き屋根の葺き方が、一度に見ることのできる貴重な造りのようです。 |
 |
 |
どんどん葺き上がっていきます
茅の匂いがとても心地よく、
なつかしい雰囲気を出しています |
いろんな形の道具で屋根面を整えていきます |
 |
 |
軒先の隅っこは90センチくらいの厚みがありそう
とても迫力があります |
屋根の棟の部分を内側から覗く
南側(切妻)の部分 |
 |
 |
| 入母屋造りの対面所(北側)の屋根 |
屋根の上は地面より暑いです。
びっしょり汗をかきながらの作業が続いています |
 |
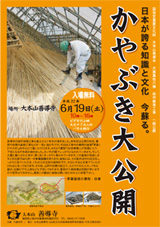 |
茅葺き屋根工事でしか見ることの出来ない
様々な道具たち |
|
|
|
|
|
|
   
現場をうろうろするので名前が 『玉監督』 (王監督ではありません…)。
ヘルメットも似合うようになりました! 一応、まじめに(?)働いています……。
休憩時間が少し多いのがタマにキズ…。
最近暑くなってきたので、夜中は、茅葺屋根の下が居心地がいいようです。
ネコも涼しいのでしょうね!
|